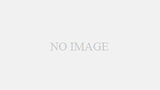背景
ある10代のお子さんが、風邪のような症状(咳や鼻水、微熱など)で近隣のクリニックを受診されました。初回の診察では、風邪薬に加えて気管支拡張剤である「メプチン(プロカテロール)錠」が処方されました。
その後、ご自宅でお薬を飲みながら様子を見ていたものの、まだ少し咳が残っていたため、再度同じクリニックを受診。
2回目の受診でも、初回と同じ風邪薬とメプチン(プロカテロール)錠が処方されることになりました。
そして処方せんを持って、お母さんと一緒に薬局に来られました。
お母さんとの会話で気づいたこと

「こんにちは。今日も前回と同じ「メプチン(プロカテロール)錠」が処方されていますね。お子さんの咳はその後いかがですか?」

「少し良くなった気はするんですが、まだ続いていて…。」

「なるほど。ちなみに、前回のお薬を飲んだときに手が震えたり、ドキドキしたりはなかったですか?」

「あっ……そう言われてみると、この前朝起きた時に「手が震える」って言ってました。もしかしてお薬の副作用なんですか?

「その可能性はあります。今日の診察のときに、そのことは先生にお伝えになりましたか?」

「いえ、すみません…。すっかり忘れてしまって、何も言っていません。」

「大丈夫ですよ。念のため、こちらから先生に確認させていただきますので、少々お時間をいただけますか?」
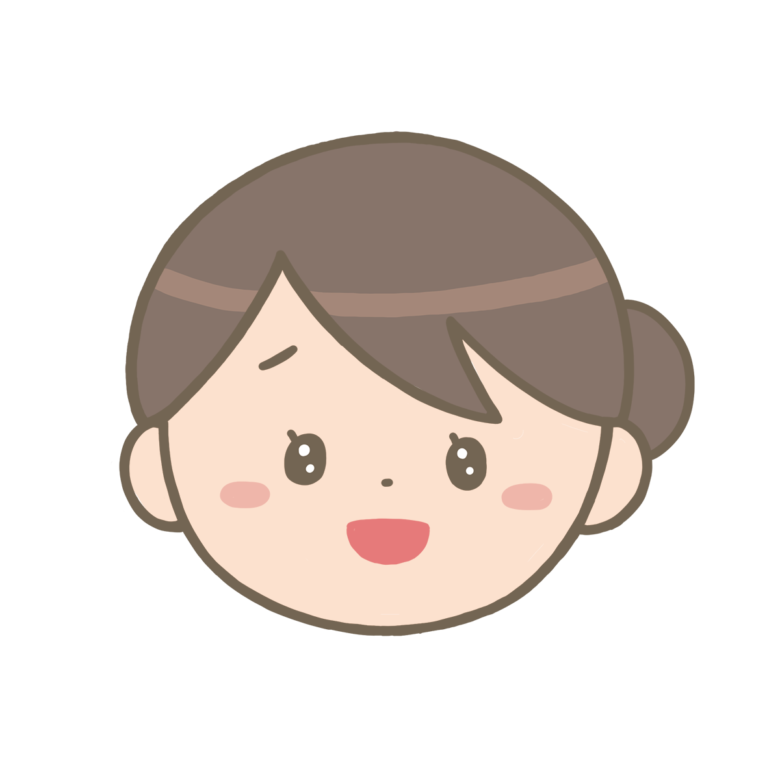
「ありがとうございます、お願いします。」
(医師に電話で確認)

「先生からご連絡がありました。今回は「メプチン(プロカテロール)錠」は中止になりました。」

「ありがとうございます。中止になって安心しました。」

「そうおっしゃっていただけて良かったです。お子さんのちょっとした変化でも、早めに気づくことがすごく大切だと思います。今回のように薬の影響かもしれない症状があったときは、どんな小さなことでも遠慮なく教えてくださいね。
なぜ注意が必要なのか?
「メプチン(プロカテロール)錠」は、気管支を広げるβ2刺激薬というお薬です。喘息や咳症状の緩和に使われますが、交感神経を刺激する作用があるため、以下のような副作用が現れることがあります。
主な副作用とその理由
| 症状 | 原因 | 備考 |
|---|---|---|
| 手の震え(振戦) | 筋肉のβ2受容体刺激 | 特に小児や高齢者で起こりやすい |
| 動悸(ドキドキ感) | 心臓のβ1受容体への影響 | 心疾患がある場合は特に注意 |
| 不安・興奮・不眠 | 中枢神経刺激作用 | 夜間の服用で悪化する場合あり |
なぜ小児や高齢者に副作用が出やすいのか
小児(子ども)の場合
- 肝臓や腎臓の代謝機能が未発達であり、薬の代謝・排泄が遅くなることがあります。
- 神経系や心臓血管系がまだ成長段階にあり、交感神経刺激に対する感受性が高いため、震えや動悸といった副作用が出やすい傾向があります。
- 体重に対して過剰投与になりやすい(体重あたりの用量設定が適正でない場合)
高齢者の場合
- 高齢になると、薬を分解したり体の外に出す働きが弱くなって、薬が体に長くとどまることがあります。そのため、副作用が出やすくなることもあります。
- 高齢になると、体の反応が変わって、同じ量の薬でも若い人より強く効いてしまうことがあります。
- ほかの薬との飲み合わせや、持病(高血圧や不整脈など)があると、副作用が出やすくなることがあります。
心疾患のある方・心臓の薬を服用中の方へ
β2刺激薬は心臓にも影響を与えるため、心疾患がある方や心臓の薬を飲んでいる方では、病状を悪化させる可能性があります。
今回のように「手の震え」など軽微に思える副作用でも、必ず医療者に報告することが重要です。
まとめ
- メプチン(プロカテロール)錠は副作用として手の震えや動悸が出ることがあります。
- 副作用に気づいたら、必ず医師や薬剤師に伝えて下さい。
- 自己判断で継続せず、専門家の判断を仰ぐことが安心・安全につながります。